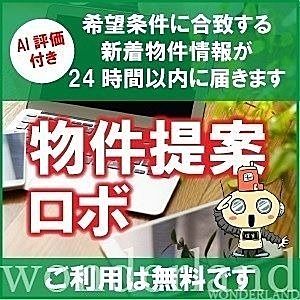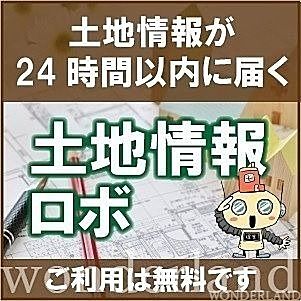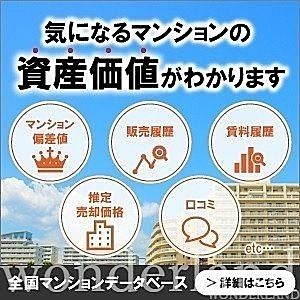未登記建物を相続したらどうする?登記する?しない?
不動産・相続について勉強中の、ワンダーランドMAIMAIです。
「建物を相続したはずなのに、そもそもその建物の登記情報が見当たらない…」というケースが珍しくありません。
特に、古くからある家屋や増改築を重ねた建物などで“未登記”のままになっていることが多いのです。
いざ相続の手続きをしようとしたときに初めて「実は建物自体が登記されていない」と判明し、戸惑う方も少なくありません。
今回は、未登記の建物を相続した場合に「登記をすべきか、それとも現状のままでもいいのか」という迷いに対して、選択肢と注意点をお伝えします。
1.なぜ未登記のままになっている建物があるのか
本来、新築や増改築が行われた際には登記手続きをすることが望ましいとされていますが、昔は「とりあえず建てたあと、名義変更や登記を後回しにしてしまった」というケースがよくありました。
また、土地は登記されていても建物の登記はされていないケースも見られます。
申請主義(登記は義務ではなく申請者が自主的に行う制度)が日本の制度として根付いているため、「特に大きな問題がないから」という理由で放置され、未登記建物のまま年月が経過してしまうのです。
2.未登記建物を相続したときに起こり得る問題点
相続においては、誰が不動産(建物)の所有者なのかを明確にしておくことが重要です。
未登記建物の場合、法務局に所有者としての情報が登録されていないため、相続登記をしようにも「そもそも登記記録が存在しない」という状況になります。
将来的に売却や抵当権の設定を考えているなら、建物が登記されていないと手続きがスムーズにいかない場合があります。
銀行から融資を受ける際にも、担保として建物の登記情報が必要になることがほとんどです。
こうした面から、未登記を放置すると資産としての活用に制限がかかる可能性があるのです。
3.登記をする場合のメリット
未登記建物を相続したあと、あらためて登記を行うことで得られるメリットはいくつかあります。
まず、法務局に正式な所有者として登録されるため、「自分(または相続人)が所有する建物」であることを証明しやすくなります。
また、売却や相続、贈与などの手続きを円滑に進めたいときにも、登記があるほうが書類手続きが明確です。
物件の価値を客観的に示すうえでも、建物の登記は大きな意味を持ちます。
たとえば、中古住宅の売却時に建物登記がない場合、買主の不安要素になり、交渉が難航することも考えられます。
適切に登記されている建物のほうが、売却などの将来的な方針を立てやすいといえるでしょう。
4.登記をしないままでいる選択肢とリスク
一方で、「今のところ住む予定もなく、売却の予定もない。わざわざ登記費用をかけたくない」と考えて未登記のままにしている方もいます。
建物を解体して更地にする計画がある、あるいは建物が老朽化しており事実上の価値が低い場合などは、必ずしも急いで登記をする必要がないという見解もあるでしょう。
ただし、いずれ誰かが利用したり売却したりしたいと考える時期がくるかもしれません。
そのときになって登記をするとなると、相続人の関係がさらに複雑になっていたり、手続きに余計な時間がかかってしまうことがあります。
将来のトラブルを防ぐ意味でも、相続のタイミングで建物を登記しておくほうが安心という考え方もあるのです。
5.建物登記の手続きの流れ
未登記建物を相続して登記する場合、まずは建物の「表題登記」が必要となります。
これは土地家屋調査士が現地調査を行い、建物の構造や面積などを確認したうえで書類を作成し、法務局へ提出します。
表題登記が完了した後、所有権保存登記や所有権移転登記を申請することになるのが一般的な流れです。
必要となる書類としては、土地家屋調査士が作成する図面や、相続関係を示す戸籍謄本、遺産分割協議書などが挙げられます。
建物の新築時と違い、すでに建っている家屋の登記は現況調査が必須なので、専門家に依頼すると比較的スムーズに進められます。
6.相続人同士の話し合いと専門家の協力
未登記建物を相続する際には、相続人全員がその存在を把握しているかどうかが大切です。
ときには「そんな建物があったの?」という状況が発生することもあり、相続人間で認識に差が出てしまうことがあります。
また、「登記費用は誰が負担するのか」「将来的に解体して土地を活用する場合はどうするのか」など、事前に話し合いをしておくべきポイントは多岐にわたります。
こうした調整には、司法書士や土地家屋調査士、不動産に詳しい税理士などの専門家の力を借りると、手続きがスムーズになると同時にトラブルを回避しやすくなります。
相続や財産管理の問題は後回しにするほど複雑化する傾向があるため、早めの対応が肝心です。
7.将来を見据えた判断がカギ
未登記建物の登記をするかどうかは「今後、その不動産をどう活用するか」によって異なります。
相続した建物に住む予定があるなら早めに登記するメリットが大きいですし、将来的に売却や賃貸活用を考えているなら、やはり登記しておくのが望ましいでしょう。
一方で、近い将来に取り壊し予定であれば、急いで登記せずに解体してしまうという選択肢もあるかもしれません。
大切なのは、相続人間できちんと話し合い、建物の状態や活用の見込みを客観的に考えたうえで方針を決めることです。
どの選択肢を取るにせよ、情報不足や認識のズレがあると後々大きな問題につながる可能性があります。
8.まとめ
未登記建物を相続するというのは、一般の方にとってあまりなじみのない状況かもしれません。
しかし、実際には古い家屋などでよく見られるトラブルのもとでもあります。
登記をするかしないかを迷う方は、まずは相続人全員で情報を共有し、建物の現況や将来プランを整理することから始めてみてください。
困ったときには、ぜひ専門家に相談することをおすすめします。
費用や手間のかかり具合、相続人間の意向調整など、ひとつひとつをクリアにしながら進めることで、後々の争いや余計な出費を防ぐことができます。
大切な財産を円滑に管理し、次の世代にもスムーズに引き継いでいくために、ぜひ早めの段階で行動していただければと思います。
******************************
不動産に関するお困りごとがありましたら、ぜひワンダーランドにご相談ください。
⭐︎☆ 有限会社ワンダーランド☆⭐︎創業:平成2年4月
・HP: https://www.0120720901.com/
https://www.720901.com/
https://www.720.co.jp/
・mail kuma@720901.com
住所:大阪市浪速区敷津西1-1-25
Tel: 0120-720901(なにわくで一番)
Tel: 0120-720981(なにわくは一番)
Fax: 06-6643−3363
Fax: 06-6647-3363
○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

関連した記事を読む
- 2025/04/25
- 2025/04/20
- 2025/04/19
- 2025/04/15